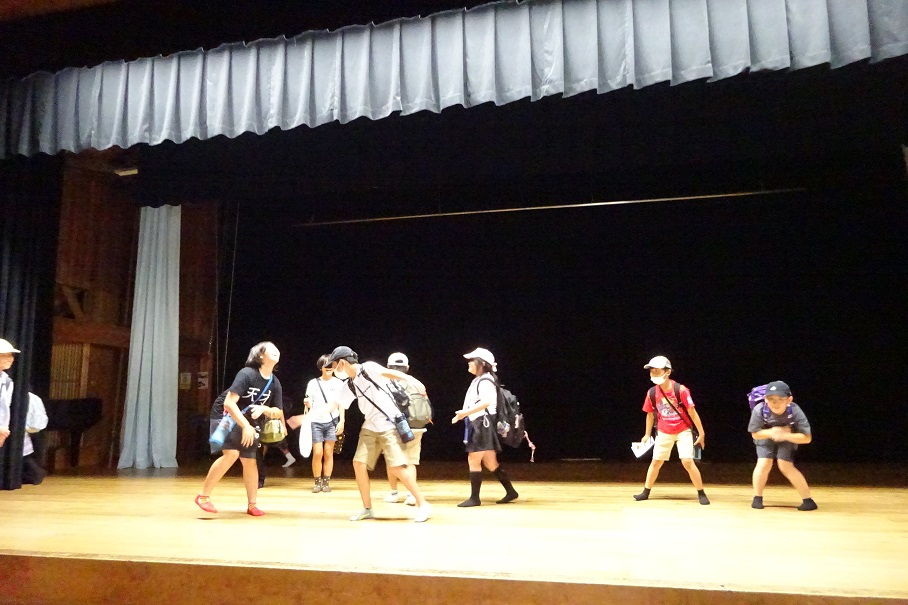第2回の歴史文化教室は、県境の町高知県梼原町と愛媛県鬼北町を訪問しました。今回の参加者は、児童18名、指導者3名の計21名です。なお、本事業は、桝山教育振興会の助成により実施しています。
まずは、梼原町。梼原町は、幕末に多くの志士たちがこの梼原を通って土佐藩を脱藩し、新しい世(明治維新)づくりに奔放した場所です。彼らの中には、大洲を通って山口(長州藩)や京に向かった者もおり、我が大洲市とも関わりがある場所と言えます。
最初に見学したのは、「梼原町歴史民俗資料館」。館内には、平安時代以降の歴史資料がたくさん展示してあり、熱心にメモを取ったり、みんな興味深く見学をしていました。もちろん、梼原から脱藩をして活躍した志士の展示も熱心に学びました。
次に、「ゆすはら座」を訪れました。ここは、昭和23年に造られた高知県では唯一の木作りの芝居小屋で、芝居や歌舞伎、映画の上映など住民の娯楽の場として親しまれた場所です。子どもたちも建物に入るとすぐに舞台を目指し、広い舞台で駆け回っていました。
梼原には、世界的に有名な建築家 隈研吾氏の建築物かたくさんあります。続いては、その中の一つ「ゆすはら雲の上の図書館」に行きました。本と木組みに包まれた森のような図書館で、木漏れ日のような光で満ち溢れた空間で、いつの間にか子どもたちも本を手に取り、読書にふけっていました。
梼原最後の見学地は、「三嶋神社」です。まず、神社に続く屋根付き橋「神幸橋」や神社の前を流れる梼原川の河原で昼食をとりました。暑い日でもあったため、食事を終えた子どもたちは、きれいな川に惹きつけられていました。この地域を開いた津野経高がこの三嶋神社を勧請して1100年。ずっとこの地域の心の支えをなってきた三嶋神社。みんなでお参りをしました。その後、境内のすぐ隣には、脱藩の道が整備されており、みんなも志士になったつもりで、しばらく脱藩の道を駆け上がりました。
博物館への帰り道、二つ目の学習の地鬼北町明星が丘にある「鬼北町歴史民俗資料館」を訪れました。鬼北町で行われている鬼の作品展や昔の生活用具などを見学し、日吉地区の人々に暮らしを学びました。特に、併設されている「武左衛門一揆記念館」では、江戸時代に起こった吉田藩の悪政から農民を守った武左衛門の偉業について興味深く学びました。
子どもたちは、大洲とはまた違った地域の人々の生活や歴史を学ぶことができ、大変充実した一日となったようです。